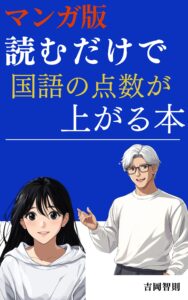大学受験勉強を始めるときに日本史を選択するか、世界史を選択するかで悩む人もいるのではないでしょうか? この先一年通して受験勉強していく中で初めにくる重要な選択となります。
仮に選択した科目が苦手では勉強も続きませんよね。後から後悔しないためにも、しっかりとそれぞれの特徴を理解して自分に合った教科を選びましょう。
日本史と世界史のどっちを選択したらいい?
日本史の特徴
では初めに日本史の特徴について見ていきましょう。
日本史の特徴は、時系列で覚える・暗記が楽・細かい暗記が必要の3つが挙げられます。以下で詳しく説明していきます。
時系列で覚えていく
日本史は対象の地域が世界史と違って狭いため、その分一つの出来事について深く学ぶことになります。1人の人物にフォーカスして学ぶこと、
時間的な流れをしっかりと理解すること、個々の事象について、そこから展開される物事の流れを掴むことなどです。
そのため、日本史は「歴史を縦に見ること」すなわち時系列で見ていくことが重要になってきます。
暗記が楽
日本史は通史と文化史に分けられ、とても細かいところまでの暗記が必要になるため、暗記が大変だと思う人もいるかもしれません。
では、なぜ日本史の暗記は楽だと言えるのでしょうか。日本史は多くの人が中学校で学んできていると思います。
そのため、ある程度の基礎ができた状態で勉強を始められます。また、日本史は世界史と違い日本のことだけを学べば良いので、並行した暗記方法を取らなくていいのです。
このようなことから日本史の暗記は楽だと言えます。


修学旅行の人気スポット:金閣寺
細かい暗記が必要
先ほども述べた通り、日本史には細かい暗記が必要になります。特に文化史は、絵画や彫刻、仏像の名前やその作者の名前まで覚えなければなりません。
仏像や絵画の名前は難しい漢字も多いため、しっかりと覚えなければ細かいところまで試験で問われたとき答えることができません。
そのほか、時代によっては経済史や社会史など、日本史の通史や文化史から少し離れた分野も細かく暗記する必要があります。
世界史の特徴
次に世界史の特徴について解説していきます。日本史との違いを意識しながら読んでみて下さい。
横のつながりで覚える
世界史の暗記方法として横のつながりで覚える、と言うことです。世界史は日本史とは違い世界各国のことを覚えます。
そのため日本史に比べ浅い暗記になりますが、その分広く覚えなければなりません。また、問題の問われ方として、「ギリシャでこのようなことが起こっているとき、この国ではどのようなことが起こっていましたか?」というように聞かれることがあります。
そのため、同時期に違う場所で起こった出来事を把握しておかなければならないのです。このように、世界で起こることを平行して覚えていく必要があるため、「横のつながりで覚える」必要があるのです。
暗記量が多い
先ほども述べた通り、世界史は世界各国のことを覚えます。そのため、世界中の条約や歴史的人物、事件などを全て覚えなければなりません。
これは通史の話ですが、さらにここに文化史も覚える必要が出てきます。また、世界で起こったことを学ぶのですから、世界地図がある程度頭に入ってないといけません。
当然ですが世界は日本よりも広いため、ここでも世界史の暗記量が多いと言えるでしょう。
また、時系列的にも世界史のほうが広いです。日本史だと1800年くらいですが、世界史だと3000年くらいになります。
下記のローマのコロッセオなどは紀元前の話ですし、漫画キングダムの時代も紀元前のお話になります。


古代ローマの遺跡
理解するのが難しい場合がある
世界各地の歴史や文化史を学ばなければならない世界史。
そのため、世界各地の背景にある出来事などを簡単にでも把握しておかなければ授業で先生の話を聞いていたときに理解が追いつかない場合があります。
また、先ほど述べた「横のつながりで覚える」というところで、どことどこが繋がっているのかわからず難しいと感じることがあります。
日本史と世界史どっちを選択するべき?
では、具体的に日本史と世界史どちらが良いのかについて解説していきます。
勉強しやすい方は?
これまで日本史と世界史の特徴や共通点について解説してきました。
勉強しやすい方と言っても一人一人得意なことが違うため確実にどちらかとは言えません。ですから、各教科の特徴を考えて、自分がどちらが勉強しやすいのかを選ぶ必要があります。
中学校で両方の科目の授業を受けていると思いますから、その時に勉強しやすいと思った教科を選ぶのが良いでしょう。
どうやって決めればいい?向き不向きは?
どのように決めたら良いのか迷う人も多いでしょう。明確にこのように決めなければならないことはありません。
そのため、自分にはどちらが合っているのかを見極める必要があります。例えば、どちらの現段階で教科に興味があるのか、単純に入り込めそうなのはどちらか、というような感じです。また、
世界史はカタカナが多く、日本史は漢字の暗記が多くなります。自分が漢字は苦手だと思うのであれば世界史を選ぶのも良いですし、逆にカタカナが苦手だと思えば日本史を選ぶのも良いでしょう。
日本史派?世界史派?
あなたはどっちですか?
漢字が苦手で、カタカナが比較的多い世界史に僕は逃げました。。。 pic.twitter.com/MNjQMRxxXD
— さわへん@気楽に行こうよ! (@sawahen_oty) October 25, 2023
おすすめの参考書は?
ここまでで自分がどちらの方がいいのか目星がついた方はいるでしょうか?教科が決ったら勉強に取り組んでみましょう。その際に必要になる参考書について紹介します。
日本史
・『日本史B 一問一答 2nd edit 完全版』
こちらの参考書は、日本史の知識を固めたい方におすすめです。中堅大学以上を狙う方はやっておきたい1冊。日本史に出てくる言葉をほぼ全て網羅しているため、もれなく勉強することができるでしょう。
・『実力をつける日本史100題』
こちらの参考書は、日本史の大まかな知識が大体インプットされた方におすすめです。各時代の重要事項などがまとめられており、解説もしっかりしているため、難関大学を狙う方にはおすすめの参考書になります。
・『金谷の「なぜ」と「流れ」がわかる本』
こちらの参考書は、日本史を始めて勉強する方でもわかりやすく時代の流れが掴むことができます。全4冊でシリーズ化されており、中堅私立や共通テストレベルとなります。
難関大学を目指している際には情報量が少ない可能性があるため、こちらの参考書にくわえて別の参考書も活用するといいでしょう。


日本史はお寺や仏像の名前まで覚える
世界史
・『山川一問一答 世界史』
こちらの参考書は、多くの高校で参考書として使われています。大学受験で必要な単語が基礎から応用まで書かれているため、あらゆるレベルに対応可能です。
・『ヨコから見る世界史 パワーアップ版』
こちらの参考書は、題名の通り世界史をヨコから見ることができるため、通史の勉強をしたい人におすすめです。一つの事件から他の事件に紐付けて覚えることができるのも魅力の一つです。
・『実力をつける世界史100題』
こちらの参考書は日本史でも紹介した参考書の世界史バージョンとなります。解説の量も多く、尚且つ難関大学にも対応できるので、中堅大学以上を目指す人におすすめの参考書になります。
表・イラストなども多用されているため、史料を確認する手間がないのも魅力的です。参考:
まとめ:日本史と世界史はどっちを選択すべきか?
✔︎日本史と世界史の特徴
✔︎日本史と世界史どっちを選べばいのか?
✔︎おすすめの参考書
について解説してきました。これから受験勉強を始める、というときの参考になれればと思います。受験勉強頑張って下さいね!


フランス:ジャンヌダルク像
O&A:日本史と世界史はどちらがきついですか?
結論としてどちらもそれなりにきついです。強いて言えば日本史のほうが平均点には早く到達するでしょう。
とはいえ、どちらもきついのですがそれが嫌な場合は政治経済などを選択すると覚える量が減ります。早稲田大学などは政治経済選択で進学してきた生徒が多くいます。
ただし、受験する大学や学部が一部制限されます。
Q&A:日本史と世界史で楽なのはどっちですか?
上記の質問と似ていますが微妙に回答が異なります。
高得点を取って社会を武器にしたい場合は世界史が良いでしょう。
満点近くを取ることも可能な科目です。そうすると入試自体が楽になります。
社会を武器にする必要が無く
あまり時間をかけたくない場合は日本史が良いでしょう。
日本史は満点近くを取るのは至難の業ですが
ある程度の点数ならば比較的に短時間で到達するからです。
さらに楽をしたければ政治経済がおすすめです。
しかし、やはりそれなりの勉強量が必要となります。
なので、好きだと思える科目を選択するのが最終的には良いでしょう。
もしくは嫌いな感じが一番少ないマシなものを選ぶと良いかと思います。
日本史と世界史どっちが好き?
— さんらいず (@sunrisewmmt) December 13, 2023
Q&A:共通テストで日本史か世界史どちらを選択するべき?
理系の場合は負担の少ない倫理などを選ぶと良いでしょう。
文系でそれほど時間をかけたくないのであれば日本史が良いかと思います。
共通テストでは漢字の記述もありませんし、
ある程度の点数までは短時間でいくと思います。
関連記事
意外と受かる⁉早稲田大学で偏差値が低い学部の魅力と特徴
大学のオープンキャンパスに行かずに受験するのはもったいない
日本史の授業で有名な阿弖流為(アテルイ)や安部氏の子孫は?
夏目漱石の面白エピソード集:負けず嫌いな甘い物好き文豪の素顔